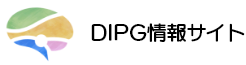プロトコールには明記されていませんが、放射線治療終了まで(初回入院中)を目安として、登録可能とします。診断時〜初回治療判定時までの、必要な情報を不足なく報告できるよう、ご注意ください。画像中央診断のメリットを活かせるよう、可能な限り早期の登録を推奨します。
-
Q1
診断直後に研究の説明をするのが難しく、同意を取得するまでに時間がかかりました。いつまでに登録しなければなりませんか?
A1 -
Q2
画像中央診断で unlikely と判断されました。登録は中止されますか?
A2画像中央診断は、あくまで参考です。症例登録後は、自施設の方針に従って診療を行い、研究登録は継続してください。
-
Q3
フォローアップ診察時に「症状チェック問診票」を使い忘れました。どうすれば良いですか?
A3可能な限り、次のタイミングで回収をお願いします。
「症状チェック問診票」は、あらかじめ患者さんの手元にあるよう、退院時や前回受診時に、お渡ししておくことをお勧めします。
症例登録時の画像提出用レターパック等と一緒に、プリントした問診票を事務局より送付致します。
患者さんが持参し忘れた時は、外来診察前の待ち時間で記載してもらってください。
問診内容は、先生方の診察の際にお役立ていただけるものと考えています。ぜひ積極的にご利用ください。 -
Q4
在宅医に紹介し、在宅医療メインに移行しました。REDCapからのCRF入力や、問診票の回収・送付はどうしますか?
A4研究参加施設(登録施設)の研究分担医師から、引き続き報告してください。
在宅医に紹介後も、研究参加施設での定期受診の際に、問診票を利用した身体所見の観察をお願いします。支持・緩和療法薬の使用状況については、在宅医と連携し、必要な診療情報を入手していただくようお願いします。病院受診が困難となった場合も同様です。
大変なお手間を取らせて申し訳ございませんが、連携を深めること、支持・緩和医療の現状を明らかにすること、が研究の目的の一つです。
難しい状況があれば、事務局にご相談ください。サポートできる事を一緒に考えさせていただきます。 -
Q5
患者が家庭・療養環境の問題で遠方に転居し、転居先の病院に紹介することになりました。研究はどうすれば良いでしょうか?
A5紹介病院がDIPG-2023研究参加施設であれば、REDCapで転院手続きをお願いします。*転院手続き後は、その症例に関するデータ入力ができなくなるため、その時点までのデータ入力を完了した上で、転院手続きをしていただく必要があります。
そうでない場合には、大変なお手間を取らせて申し訳ございませんが、可能な限り転院先から情報を得て、定期観察の継続をお願いいたします。
難しい状況があれば、事務局にご相談ください。サポートできる事を一緒に考えさせていただきます。